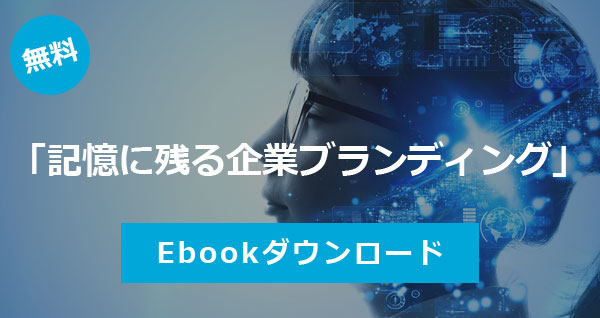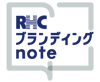SDGs9「産業と技術革新の基盤をつくろう」の詳細を事例を交えて紹介!
SDGs

産業化を進めつつ外的要因からの復元力ある社会基盤づくりを目指す
これに付随して、以下のターゲットが設定されています。外務省の資料より引用してご紹介します。
●「目標9.産業と技術革新の基盤をつくろう」のターゲット
9.1 すべての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラを開発する。
9.2 包摂的かつ持続可能な産業化を促進し、2030年までに各国の状況に応じて雇用及びGDPに占める産業セクターの割合を大幅に増加させる。後発開発途上国については同割合を倍増させる。
9.3 特に開発途上国における小規模の製造業その他の企業の、安価な資金貸付などの金融サービスやバリューチェーン及び市場への統合へのアクセスを拡大する。
9.4 2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。すべての国々は各国の能力に応じた取組を行う。
9.5 2030年までにイノベーションを促進させることや100万人当たりの研究開発従事者数を大幅に増加させ、また官民研究開発の支出を拡大させるなど、開発途上国をはじめとするすべての国々の産業セクターにおける科学研究を促進し、技術能力を向上させる。
9.a アフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国及び小島嶼開発途上国への金融・テクノロジー・技術の支援強化を通じて、開発途上国における持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラ開発を促進する。
9.b 産業の多様化や商品への付加価値創造などに資する政策環境の確保などを通じて、開発途上国の国内における技術開発、研究及びイノベーションを支援する。
9.c 後発開発途上国において情報通信技術へのアクセスを大幅に向上させ、2020年までに普遍的かつ安価なインターネット・アクセスを提供できるよう図る。
(出典:外務省仮訳「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」)
インフラ整備が遅れている地域への支援により全体的な生産性の向上を図る

インフラの整備は、地域の開発や産業の発展に直結し、経済成長を促進する重要なポイントです。
水や電力供給などについては他の目標でも触れてきましたが、SDGsはさまざまな課題を包括的に取り上げているため、ここでもターゲットとされています。
特に開発途上国におけるインフラ整備は、生活を安定させ、水や電力を得るために労働力を割くことから産業の生産性を上げる方向へベクトルを向けることができるため、政府や民間組織が支援を続けています。
また、ターゲット9.1にある「強靱(レジリエント)なインフラ」という点について解説しますと、「レジリエント」は「復元力、回復力、弾力性のある」といった意味の言葉です。
例えば「災害レジリエントなインフラ」「気候変動レジリエントなインフラ」「レジリエントなまちづくり」のように使われ、元の状態に回復できることを指しています。
こうした復元力のあるインフラづくりが、世界で求められているといえるでしょう。
世界における産業と技術革新の基盤をつくるための取り組み

1970年から1993年まで長く内戦状態にあったカンボジアでは、インフラが破壊され、その復旧も遅れていました。
首都プノンペンでも、1993年時点での水道普及率は約25%という低さで、その支援に日本が着手。マスタープランを策定し、北九州市の上下水道局が現地で指導に当たりました。
それまでは漏水や違法な分岐による盗水、また水道料金の非徴収率などが高く、正常な管理ができていない状態で、給水も1日10時間しかできていなかったとのこと。
そのプノンペンの水道公社に対し、インフラ復旧の技術支援を行い、水道の敷設から維持管理方法、水道料金の徴収体系などを指導することにより、安全な水の供給に貢献したのです。
この事業は「プノンペンの奇跡」として世界中に知られることとなり、SDGsの成功事例として取り上げられています。
さらに2010年には「北九州市海外水ビジネス推進協議会」が発足し、約150社(2020年3月2日現在)の企業が参画して日本の水道技術を他国に輸出する取り組みへと発展しています。
●団体の取り組み事例/JICA
JICA(独立行政法人国際協力機構)は、日本の政府開発援助(ODA)を行っている機関です。
アフリカのルワンダでは、電力供給に関するプロジェクトを実施しました。
ルワンダでは全国での世帯電化率は5%、電化されている都市部でも25%という低さで、都市部でも配電設備の劣化により停電が頻発。経済成長を妨げるネックとなっていました。
発電設備や配電設備に関しては、政府による計画が進められていましたが、これを管理するルワンダ電力公社の人材不足や技術力向上の問題の解決が必要とされていたのです。
そのため、JICAでは技術者を育成する「効率的な電力システム開発のための能力開発プロジェクト」を実施。訓練センターの機能を強化しつつ、効率的な電力システムを実現する配電網のデータベースの構築の支援に取り組みました。
その結果、安定的な電力供給に向けた体制が整えられていき、育成された人材によるデータベースの運用・維持管理が行われているとのこと。プロジェクト完了後も、持続的にこの体制を維持することが必要とされています。
地球上の誰ひとり取り残さないためのSDGs17の目標
では17の目標を見てみましょう。
【持続可能な開発目標】
SDGs1.貧困をなくそう
SDGs目標1「貧困をなくそう」は、「あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ」ことを目的としたものです。
SDGs2.飢餓をゼロに
「目標2.飢餓をゼロに」は、「飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する」ことを目的としたものです。
SDGs3.すべての人に健康と福祉を
SDGs目標3.「すべての人に健康と福祉を」は、「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する」ことを目的としたものです。
SDGs4.質の高い教育をみんなに
SDGs目標4.「質の高い教育をみんなに」は、「すべての人々への、包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する」ことを目的としたものです。
SDGs5.ジェンダー平等を実現しよう
SDGs目標5.「ジェンダー平等を実現しよう」は、「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う」ことを目的としたものです。
SDGs6.安全な水とトイレを世界中に
SDGs目標6.「安全な水とトイレを世界中に」は、「すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する」ことを目的としたものです。
SDGs7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに
SDGs目標7.「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」は、「すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する」ことを目的としたものです。
SDGs8.働きがいも経済成長も
SDGs目標8.「働きがいも 経済成長も」は、「包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する」ことを目的としたものです。
SDGs9.産業と技術革新の基盤をつくろう
SDGs目標9.「産業と技術革新の基盤をつくろう」は、「強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る」ことを目的としたものです。
SDGs10.人や国の不平等をなくそう
SDGs目標10.「人や国の不平等をなくそう」は、「各国内および各国間の不平等を是正する」ことを目的としたものです。
SDGs11.住み続けられるまちづくりを
SDGs目標11.「住み続けられるまちづくりを」は、「包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する」ことを目的としたものです。
SDGs12.つくる責任 つかう責任
SDGs目標12.「つくる責任 つかう責任」は、「持続可能な生産消費形態を確保する」ことを目的としたものです。
SDGs13.気候変動に具体的な対策を
SDGs目標13.「気候変動に具体的な対策を」は、「気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる」ことを目的としたものです。
SDGs14.海の豊かさを守ろう
SDGs目標14.「海の豊かさを守ろう」は、「持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する」ことを目的としたものです。
SDGs15.陸の豊かさも守ろう
SDGs目標15.「陸の豊かさも守ろう」は、「陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する」ことを目的としたものです。
SDGs16.平和と公正をすべての人に
SDGs目標16.「平和と公正をすべての人に」は、「持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する」ことを目的としたものです。
SDGs17.パートナーシップで目標を達成しよう
SDGs目標17.「パートナーシップで目標を達成しよう」は、「持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する」ことを目的としたものです。
これらは地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを前提に定められたもの。その背景には、前身であるMDGsが発展途上国の問題の解決にウエイトが置かれており、偏りがあると指摘されていたことがあります。
改めて地球上のすべての人が協力して取り組むべき目標として掲げられたSDGs。
17の目標それぞれの詳しい内容やターゲット、事例については、別の記事で紹介していきます。
ライタープロフィール

神澤 肇(カンザワ ハジメ)
リボンハーツクリエイティブ株式会社 代表取締役社長
創業40年以上の制作会社リボンハーツクリエイティブ(RHC)代表。
企業にコンテンツマーケティングを提供し始めて約15年。
数十社の大手企業オウンドメディアの企画・制作・運用を担当。
WEBを使用した企業ブランディングのプロフェッショナル。
映像業界出身で、WEB、紙媒体とクロスメディアでの施策を得意とする。
趣味はカメラとテニス、美術館巡り、JAZZ好き。