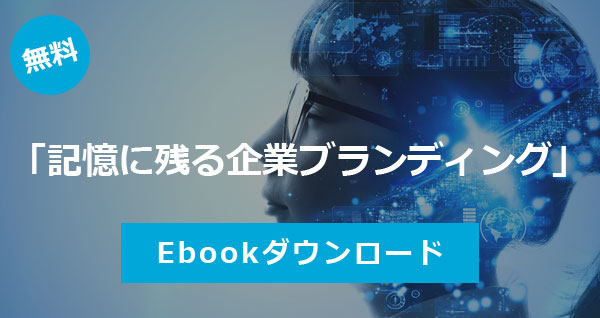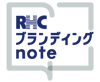ブランドアイデンティティとは?構成要素や作り方まで分かりやすく解説
ブランディング

ブランドアイデンティティという言葉を聞いたことがあるものの、具体的にどういった概念なのか理解できていない。
本記事は上記のような方に向けて、ブランドアイデンティティの意味や主な構成要素、構築することで得られるメリットについて分かりやすく解説します。
具体的な作り方や企業事例についてもご紹介していますので、ぜひ最後までご確認ください。
ブランドアイデンティティとは

まずはブランドアイデンティティの定義や、ブランドイメージなどとの違いについてご紹介します。
ブランドアイデンティティの定義
ブランドアイデンティティとは、「ブランドが提供する価値や世界観」などを表した概念です。ブランド論の大家デービッド・アーカー氏は以下のように定義しています。
“そのブランドにこうなってほしいと強く願うイメージを、はっきりと言葉で示したものだ。つまり、顧客や関係者(社員や事業パートナーなど)の目から見たとき、そのブランドが表してほしいと願うものである。”
(引用:ブランド論)
アーカー氏は同書の中で、ブランドアイデンティについて「ブランド構築において中心となる概念」として捉えており、ブランドを構成する各要素を決定付ける存在であると説いています。
つまりブランドを表現するデザインやキャッチフレーズなど、あらゆる要素がブランドアイデンティティを起点に作られるのです。
ブランドイメージとの違い
ブランドアイデンティティと混同されやすい概念としてブランドイメージがあります。
ブランドイメージは、「ブランドに対して顧客が抱くイメージ」です。
対してブランドアイデンティティは、先のアーカー氏の定義にあるように、自社ブランドについて、「顧客に○○というイメージを抱いてほしい」という概念となります。
ブランディングとは、このブランドアイデンティティとブランドイメージのギャップを無くし、イコールにする取り組みなのです。
もしブランドアイデンティティとブランドイメージに大きな乖離がある場合、ブランディング上に大きな問題が生じていると言えるでしょう。
ブランドビジョンとの関係
アーカー氏は1997年の著書「ブランド優位の戦略」では、ブランドアイデンティティという言葉を使っていますが、2014年の著書「ブランド論」でブランドアイデンティティからブランドビジョンに呼称を変えています。
つまりブランドビジョンとブランドアイデンティティは基本的に同義となるのです。
企業によってブランドビジョンを「ブランドを表すキャッチコピー」と捉えるケースもありますが、本記事では「ブランドアイデンティティ=ブランドビジョン」という解釈に基づき、解説を進めていきます。
ブランドアイデンティティの一般的な構成要素

ブランドアイデンティティは複数の要素によって構成される複合的な概念です。
ここでブランドアイデンティの一般的な要素についてご紹介します。
フィロソフィー
フィロソフィーとは、その企業の哲学や考え方、価値観を表す概念であり、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)もここに含まれます。
ブランドの「存在意義」や「目指している世界観や在り方」といった点を定義する要素になります。
ブランドアイデンティティにおいて最も重要な要素であり、他の構成要素を決める上での基盤となるのです。
ベネフィット
ベネフィットはブランドを通じて顧客が得られる価値であり、以下の種類に分けられます。
| 機能的ベネフィット | 製品・サービスの機能や品質によって得られる直接的な価値 Ex.時計を購入することで時間を把握できる |
| 情緒的ベネフィット | ・製品・サービスを利用することで消費者が感じる感情的な価値 Ex.高級時計を身に付けることで、優秀なビジネスパーソンになった気分に浸れる |
| 自己表現ベネフィット | 製品・サービスを通して、理想の自分を表現できるという価値 Ex.憧れの俳優と同じ時計を付けることで、俳優と自分を同化できる |
| 社会的ベネフィット | 製品・サービスを利用することで、同じブランドを愛好する社会的集団の一員になっていると感じる価値 Ex.ブランド利用者限定のコミュニティイベントに参加できる |
フィロソフィーだけでは、「ブランドが顧客にとってどのように役立つのか」という点がどうしても抽象的になってしまいます。
ベネフィットをブランドアイデンティティに含めることで、顧客にとっての価値や便益を具体的に示すことができるのです。
属性
製品やサービスが持つ属性も、ブランドアイデンティティを構成する要素となります。
ブランドの属性とは、ブランドが提供するベネフィットの根拠となる特性のことです。
例えば環境負荷が少ないことをベネフィットとして含めている場合、「なぜ環境負荷が少ないのか」という点に対して、根拠となる以下のような要素が必要です。
・再生可能な材料で作られている
・生産工程において二酸化炭素の排出を最小限に抑えている
・リサイクルが可能
上記のような要素とそれを証明する具体的なデータが、ブランドアイデンティティにおける「属性」となり、顧客に対して信頼感を与える役割を担います。
パーソナリティ
パーソナリティとは、ブランドを擬人化した際の特徴を指します。
ブランドがどのような個性を持つかを表し、便益を端的に表して伝える役割を持ちます。
例えば「誠実で信頼できる」と「独創的かつ革新的」といったパーソナリティがあったとしましょう。
メーカーが品質面を最重視し、ベネフィットとして訴求したい場合は「誠実で信頼できる」が相応しいパーソナリティとなります。
逆に他メーカーよりも先進的な存在であることを示したいのであれば、「独創的かつ革新的」といったパーソナリティが適しているでしょう。
このように「どのように思われたいか」「どういったベネフィットがあるのか」を示す際に、パーソナリティは強力な武器となるのです。
ブランドアイデンティティを構築するメリット

続いてブランドアイデンティティを構築することで得られるメリットをご紹介します。
メリット①:ブランド戦略の一貫性を担保できる
ブランドアイデンティティはブランドの価値や存在意義などをまとめた概念であるため、そこに準拠して活動することで、ブランド戦略の一貫性を担保できます。
ブランドアイデンティティを明確にしていなければ、顧客とのコミュケーションにおいて、「自社はどういう存在なのか」「どういった価値を提供しているのか」という点が曖昧になります。
そうなると各接点において伝える内容にバラつきが生じ、顧客が抱くブランドイメージも三者三様の状態になってしまうでしょう。
ブランドアイデンティティを構築すれば、こういった事態を防ぎ、あらゆる顧客接点において一貫したメッセージを伝えられるようになるのです。
メリット②:顧客にブランドの魅力が伝わりやすくなる
ブランドアイデンティティが確立されることで、顧客にブランドの魅力を分かりやすく伝えることができます。
ブランドアイデンティティには、ベネフィットや属性、パーソナリティといった、顧客に対して分かりやすく伝えるための要素が含まれています。
これらの要素をしっかりと整理することで、顧客に対してどのような情報やメッセージを伝えれば、ブランドの魅力を正しく伝えられるのかが明確になるのです。
逆にブランドアイデンティティが曖昧なままでは、顧客に伝えるべき要素も不明瞭になるため、ブランドの持つ魅力や価値を正しく理解してもらうことはできません。
メリット③:競合との差別化を実現できる
ブランドアイデンティティは、ブランドの持つ独自性を表す役割も担うため、競合他社との差別化を実現しやすくなるでしょう。
ブランドアイデンティティの構成要素であるフィロソフィーは、理念や価値観が内包されます。
理念や価値観は、創業者がビジネスを始めるに至った経緯や背景、長い企業活動の中で醸成されていくため、独自性の高い概念となります。
そのため、たとえ機能的ベネフィットや属性といった要素で、競合との差別化が難しい製品・サービス領域であっても、フィロソフィーを軸に訴求することで、自社の独自性をアピールできるのです。
メリット④:従業員の定着や採用力の強化
ブランドアイデンティティは顧客だけでなく、従業員や求職者にとっても、強力なアピールポイントになります。
ブランドアイデンティティを確立することで、従業員は仕事の意義やビジネスに携わることへの誇りを感じやすくなり、従業員エンゲージメント(自社に貢献したいという意欲)の向上を実現できます。
その結果、従業員の定着率が高まることが期待できるのです。
また自社が目指している世界観や大切にしている価値観をブランドアイデンティティとして訴求することで、そこに共感を覚える求職者が自然と集まるようになります。
その結果、自社と親和性の高い母集団を形成できるようになり、採用力の強化やミスマッチの防止といった効果を得ることもできるでしょう。
ブランドアイデンティティの作り方

ここからはブランドアイデンティティの作り方として、「ブランド・ビジョン・モデル」をご紹介します。
ブランド・ビジョン・モデルの概要
ブランド・ビジョン・モデルとは、デービッド・アーカー氏が著書「ブランド論」の中で、提唱したブランドビジョン(以下、ブランドアイデンティティ)を生み出すためのフレームワークです。
ブランド・ビジョン・モデルを活用することで、独自性があるブランドアイデンティティを構築できます。具体的には以下のステップを踏み、ブランドアイデンティティを構築します。
1. 現状の整理・分析
2. ブランド連想の抽出とグルーピング
3. 構成要素の優先順位付け
4. ブランドエッセンスの策定
5. ブランドポジションの策定
それぞれ見ていきましょう。
ステップ①:現状の整理・分析
まずは現状の整理と分析を行います。
自社の製品・サービスの相対的な強みや弱みは勿論、競合他社の状況や顧客ニーズ、市場におけるトレンドなどを考察していきます。
これらの分析内容と企業としての事業戦略を踏まえ、どういったブランドアイデンティティを構築すべきかの方向性を見極めることになるでしょう。
またブランドアイデンティティ構成要素となりうる情報も併せて整理しておくことで、後のプロセスを効率的に進めることができます。
整理に役立つフレームワーク:ブランド・アイデンティティ・プリズム
ブランドアイデンティティの構成要素の候補を抽出する際は、「ブランド・アイデンティティ・プリズム」と呼ばれるフレームワークの活用がおすすめです。ブランド・アイデンティティ・プリズムは、アーカーと並ぶブランド論の権威であるジャン・ノエル・カプフェレ氏によって提唱されました。
ブランド・アイデンティティ・プリズムでは、以下の6つの要素を具体化することで、ブランドアイデンティティ構築に繋がる要素を整理できます。
| Physique ブランドの物理的特長 |
ブランドの製品やサービスの機能をはじめ、ネーミングやデザイン、ロゴなどの物理的な特徴 |
| Personality ブランド・パーソナリティ |
ブランドを擬人化した際の個性や雰囲気 |
| Relationship 顧客とブランドの関係性 |
ブランドと顧客との関係性 |
| Culture 文化 |
ブランドの持つ価値観や行動基準といった文化 |
| Reflection ブランドのターゲット |
ブランドのターゲットとすべき顧客像 |
| Self-Image セルフ・イメージ |
顧客がブランドを利用することで抱く自己イメージ |
ステップ②:ブランド連想を書き出しグルーピングする
現状分析やブランドアイデンティティの要素になりうる情報を整理できたあとは、ブランド連想を書き出していき、各連想をグルーピングします。
ブランド連想とは「顧客がブランドに触れた際に連想するイメージ」であり、各種ベネフィットやパーソナリティ、属性、ブランドイメージなどが該当します。
先のステップで整理した要素も参考としつつ、自社のブランドにおいて「どのようなブランド連想を獲得すべきか」を検討し、理想とするブランド連想を書き出していきましょう。
ブランド連想を書き出す際は、差別化に繋がる要素を優先的に抽出すべきですが、仮に差別化要素が少なければ、他ブランドとの等価性を示す平準化要素も併せて取り入れます。
各ブランド連想を抽出した後は、類似した連想を集めてグルーピングし、そのカテゴリの内容を端的に表すタイトルを付けましょう。
この各グループのタイトルが、それぞれブランドアイデンティティの構成要素となります。
ブランドアイデンティの構成要素について、アーカー氏は「ブランドビジョンエレメント」と呼称しています。
ステップ③:構成要素に優先順位を付ける
次にブランドビジョンエレメントに優先順位を付けます。
ブランドビジョンエレメントの内、最も重要かつ顧客に対してインパクトを与えられる要素を「コアビジョンエレメント」として策定します。
コアビジョンエレメントは多くても3つ程度に収め、その他のブランドビジョンエレメントは、拡張ビジョンエレメントとして整理しましょう。(以下の図参照)

画像:ブランドビジョンエレメントの例(ブランド論p.45 の図を基に制作)
構成要素の選択基準
ブランドビジョンエレメントの優先順位を付け、ブランドアイデンティティに取り入れる要素を選定する際は、以下の基準を参考にしましょう。
| 記憶可能性 | 記憶されやすく、注意を惹きやすいか |
| 意味性 | 記述的あるいは説得的な内容を含めているか |
| 選考性 | 好ましいイメージを持っているか |
| 移転可能性 | 同じブランドを冠した他製品・サービスのブランド構築に役立てるか |
| 適合可能性 | 顧客の価値観やニーズの変化に柔軟に適合できるか |
| 防御可能性 | 法律や競争上の観点において防御できるか |
上記はブランドマネジメントの権威であるケビン・レーン・ケラー氏が、著書「エッセンシャル 戦略的ブランド・マネジメント」で取り上げた要素です。
ケラー氏はデザインやネーミング、パッケージなどの要素を対象として上記の選定基準を提唱していますが、ブランドビジョンエレメントの選定においても参考になる観点であるため、ぜひ覚えておきましょう。
ステップ④:ブランドエッセンスを生み出す
ブランドビジョンエレメントの選定後は、ブランドエッセンスを制作します。
ブランドエッセンスとは、ブランドビジョンエレメントを踏まえ、ブランドアイデンティティの根幹となる要素を端的に表したメッセージです。
先程掲載したブランドビジョンエレメントの例の中央に記載されているメッセージ(赤枠内)が、ブランドエッセンスです。

画像:ブランドエッセンスの例(ブランド論p.45 の図を基に制作)
ブランドエッセンスは、従業員に対してブランドアイデンティティを分かりやすく伝達するためのコンセプトとして機能します。
ステップ⑤:ブランドポジションを策定する
最後のステップはブランドポジションの策定です。
ここで述べるブランドポジションとは、顧客を含めた外部に向けてブランドアイデンティティを伝達するためのキャッチフレーズのことです。ブランドコンセプトとも呼ばれます。
ブランドアイデンティティを軸に、「何を」「どのような顧客に向けて」「どのような論理で伝達するのか」の指針として機能します。
最も強い訴求力を持つブランドビジョンエレメントを、ブランドポジションとして採用するケースも多くなるでしょう。
ブランドアイデンティティを策定した後にすべきこと

続いてブランドアイデンティティを策定した後にすべき取り組みについてご紹介します。
ブランドガイドラインを定める
まず挙げられるのはブランドガイドラインの策定です。
ブランドアイデンティティは、ブランドネームやロゴ、カラーやデザイン、キャッチフレーズなど様々な要素で表現されます。
またWebサイトやソーシャルメディアは勿論、パッケージや店舗、街頭広告、営業担当者など多数の媒体上で表現されることになるでしょう。
これらの要素・媒体においてブランドアイデンティティを適切に表現するには、カラーコードやフォントなどのルールを定める必要があるのです。
また営業担当者など、顧客対応を行う従業員が守るべき行動規範や考え方なども併せて定義しておくことで、一貫したブランド戦略を実現できるでしょう。
インナーブランディングを実施する
インナーブランディングとは、従業員に対して実施するブランド浸透施策です。
ブランドアイデンティティを前提とした製品を開発したり、マーケティングコミュニケーションでブランドアイデンティティを表現したりするには、エンジニアやマーケターといった各従業員がブランドについて正しく理解している必要があります。
そのためブランドエッセンスを起点に、ブランドアイデンティティの社内浸透施策を展開しなければなりません。
具体的にはブランド勉強会や社員向けブログなどによる情報発信、ブランドアンバサダーの任用といった取り組みを実施し、従業員の理解促進を図ることになるでしょう。
アウターブランディングを実施する
インナーブランディングによって、従業員が十分にブランドアイデンティティを理解できた後は、社外に向けてブランドアイデンティティを発信していきます。
広告やWebサイト、ソーシャルメディアなどの各顧客接点において、ブランドポジションを軸に、ブランドアイデンティティを感じられるメッセージを訴求しましょう。
また営業担当者やマーケターなど、顧客対応を行う従業員の行動もアウターブランディングに大きな影響を与えます。
そのためアウターブランディングの段階に入った後も、インナーブランディングには継続的に取り組み、従業員のブランドへの理解をさらに深めていくことが重要になるでしょう。
ブランドアイデンティティの事例

最後にブランドアイデンティティの成功事例についてご紹介します。
事例①:ユニクロ
ユニクロは1984年の一号店オープン以来、「服のチカラで世界を良い方向へ変えていく」という理念を軸とした「MADE FOR ALL」というブランドアイデンティティを掲げてきました。
「MADE FOR ALL」の下、衣服を通じてあらゆる人の生活を豊かにすべく、事業を展開してきたのです。
ユニクロはSDGsにも積極的に取り組み、販売後の製品をリサイクル・リユースする仕組み「RE.UNIQLO(リユニクロ)」といった活動も展開しています。
「RE.UNIQLO」で回収された衣料は、衣服を十分に確保できない難民や困難な状況にある人々に寄贈しているのです。
これらの取り組みを通じて、ユニクロは「MADE FOR ALL」を体現していると言えるでしょう。
参考:ユニクロとSDGs | 服のチカラを、社会のチカラに。 UNIQLO Sustainability
事例②:スターバックス
コーヒーチェーン店を展開するスターバックスは、創業以来「サードプレイス」というブランドアイデンティティを掲げています。
サードプレイスとは、「自宅でも職場でもない第3のリラックスできる場所」を指します。
機能的価値であるコーヒー自体をブランドアイデンティティの中核に据えるのではなく、「スターバックスの店舗で過ごす時間や体験」をブランド価値の核としているのです。
サードプレイスを実現するために、座席数を他のコーヒーチェーン店よりも少なく配置し、ゆったりと過ごせるように設計するとともに、親近感を覚えてもらえるような接客方法を確立しています。
これらの取り組みにより、スターバックスは確固たるポジションを築き、他のコーヒーチェーン店から差別化を図っているのです。
参考:「おかえり」「ただいま」が聞こえてくる居心地の良い場所。サードプレイスの価値とは(大阪府・豊中市) - Starbucks Stories Japan
事例③:東京ディズニーリゾート
東京ディズニーリゾートは1983年の東京ディズニーランドのグランドオープン以来、「夢と魔法の王国」というブランドアイデンティティを掲げ、来場者に素晴らしい体験を提供しています。
このブランドアイデンティティを支えているのは、従業員(以下、キャスト)の高水準な接客対応にあると言えるでしょう。
東京ディズニーリゾートを運営する株式会社オリエンタルランドは、キャストに対して行動規準「The Five Keys〜5つの鍵〜」を設け、徹底させているのです。

引用:行動規準「The Five Keys〜5つの鍵〜」(東京ディズニーリゾート) | ゲストの安全・安心 | 社会 | サステナビリティ | 株式会社オリエンタルランド
各キャストが上記の行動規準を深いレベルで理解・徹底することで、「夢と魔法の王国」というブランドアイデンティティの浸透を図っています。
またパーク内から外が見えにくいように施設設計が行われており、外部空間と遮断することで、来場者がふとした拍子に現実に戻されることを防いでいる点も大きなポイントと言えるでしょう。
まとめ
ブランドアイデンティティは企業の価値観や世界観、顧客に提供する価値などを内包した概念であり、全てのブランド活動における根幹となります。
ブランドアイデンティティを明確化することで、顧客に対してブランドの魅力を分かりやすく伝えられるため、他社との差別化も実現しやすくなるでしょう。
ただし構築するには自社に関する様々な要素を整理する必要があり、長い時間や労力がかかります。
簡単に取り組めるものではないため、ブランドアイデンティティの構築を目指す際は、相応の期間とリソースを確保した上で臨む必要があるでしょう。
ぜひこの記事を参考にしつつ、魅力的なブランドアイデンティティの構築を目指してください。
ライタープロフィール

神澤 肇(カンザワ ハジメ)
リボンハーツクリエイティブ株式会社 代表取締役社長
創業40年以上の制作会社リボンハーツクリエイティブ(RHC)代表。
企業にコンテンツマーケティングを提供し始めて約15年。
数十社の大手企業オウンドメディアの企画・制作・運用を担当。
WEBを使用した企業ブランディングのプロフェッショナル。
映像業界出身で、WEB、紙媒体とクロスメディアでの施策を得意とする。
趣味はカメラとテニス、美術館巡り、JAZZ好き。