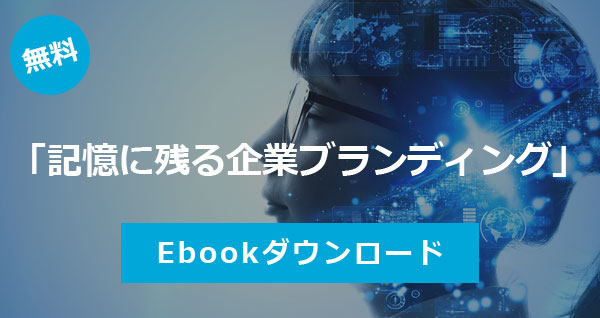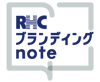箱根駅伝ユニホームが示唆する、ビジュアルアイデンティティ 細田悦弘の企業ブランディング 〈第20回〉
ブランディング

正月の風物詩ともいえる箱根駅伝。今年で98回目となりました。草創期から出場している伝統校もあれば、新進気鋭の実力校も続々と登場しています。各校のカラフルなユニホームを注意深く見てみると、ブランディングの観点から示唆に富んでいることに気づきます。
早稲田は「W」、中央は「C」、青学は「青山学院」、駒澤は「駒澤大學」
1920(大正9)年に第1回が挙行された箱根駅伝は、103年の歴史を誇ります。そのユニホームは時代とともに素材は進化し、鮮やかな色調やデザインで洗練され、実に多彩で個性にあふれています。駅伝ファンにとっては、色彩やデザインを見ただけで、「あそこだ!」と識別できることでしょう。
選手のユニホームには、各チーム統一の白地のゼッケンに大学名が記載されていますが、ユニホームに直に付された大学名表記を注視してみると、大きく3つの傾向があることに気づきます。
(1) 大学名または学校法人名を正式に表記 … 「駒澤大學」、「帝京大学」、「青山学院」など
(2) 大学名のイニシャルを大きく表記 … 早稲田の「W」、中央の「C」、明治の「M」など
(3) 大学の校章、シンボルマークを表記 … 順天堂大学、筑波大学など
戦前から出場の伝統校においては『イニシャル』が圧倒的で、1980年代以降に初出場を果たした大学の多くは正式名称の表記となっています。歴史的ある実力校は、イニシャルだけで伝わる優位性があります。一方、新興勢力の多くは大学名を浸透・認知させるために、広報活動の観点からも正式名称の表記を志向しているようです。大学ブランディングにとって、箱根駅伝は絶好のステージといえます。ブランド戦略において、スクールカラーやロゴはまさに大学のシンボルであり、「見え方(ビジュアルアイデンティティ)」は重要な役割を果たします。
大学ブランドとビジュアルアイデンティティ
大学ブランドの目指す姿を実現するには、その大学らしさの伝え方が重要です。せっかく高い差別性(得意技と個性)があっても、ステークホルダーに伝わらなければ意味がありません。「ビジュアルアイデンティティ(Visual Identity)」とは、ブランドの価値やコンセプトの視覚的な表現方法であり、シンボルマークやロゴなどを中心に、そのブランドを象徴するデザイン要素一式を指します。略すと、一般的に「VI」といいます。
箱根駅伝においては、ユニホームの色やデザインといったVIは、ブランドが目指す姿(らしさ)を瞬間で伝える威力を発揮します。私たちはゼッケンの大学名を確認するまでもなく、フレッシュグリーン、臙脂(えんじ)、江戸紫、藤色、紫紺、赤、鉄紺、茄子紺、ファイアーレッド、オレンジ、プラウドブルー等々の色鮮やかなスクールカラーによって、即座にどの大学なのかを識別できます。伝統校・名門校の風格あるイニシャルは、ブランドロゴそのものの訴求力を持ちます。
「△△といえば、〇〇大学」
エルメス、シャネル、ルイ・ヴィトン、メルセデス・ベンツ、BMW・・・。優れたブランドには強力なビジュアルアイデンティティがあります。それは、数ある競合のなかで明確な差別化へとつながり、消費者をそのブランドへと誘導します。言わば、企業の顔でもあるビジュアルアイデンティティは、他の企業や商品と識別するための標章であり、商品・サービスの品質や企業活動の信頼性の保証の印でもあり、さらには、あらゆる企業活動を通した消費者や社会に対する「約束の象徴」としての機能を果たします。
ブランドは、「〇〇といえば、△△」「△△といえば、〇〇」といった構造で成立します。この『約束』を毅然として守ることでブランドは維持されます。大学においては、「駅伝王者といえば、〇〇大学」「〇〇大学といえば、駅伝王者」を堅持するためには、生半可な意識では不可能です。選ばれ続ける存在であるためには、大学も企業も『覚悟』が必要です。会社組織もチームも、『こだわり』を分かち合えるかどうかが勝負どころとなります。
「古豪」と時代性
イニシャルを見ただけで想起される「伝統校」の領域に入ると、とかく過去の栄光のもとに『守り』に入りがちですが、時代は目まぐるしく移り変わっています。これまでの常識や既成概念にとらわれることがなく、果敢なチャンレジが不可欠です。昔(かつて)の強豪というニュアンスで「古豪」と呼ばれ出すと少し注意が必要です。本来は『伝統ある実力校』という敬意を込めた語感がありますが、時代にふさわしく磨き上げる不断の努力が強く求められます。これは、老舗企業にも当てはまります。
ビジュアルアイデンティティは、歴史ある企業や大学にとって最大のイメージ資産です。これまで築き上げてきたブランドの資産(brand equity)や価値観を、万古不易の部分と時代の変化に対応する部分をブレンドさせることが大事です。ブランドに『時代性』を備えるところに、「サステナブル・ブランディング」の核心があります。時代性とは環境の変化をしなやかに捉え、それに応じることです。
「らしさ」を存分に発揮しながら、時代に適合し、時代と調和し、時代を味方につけるのがサステナブル・ブランディングの要諦です。
ライタープロフィール

細田 悦弘(ホソダ エツヒロ)
公益社団法人日本マーケティング協会「サステナブル・ブランディング講座」講師 / 一般社団法人日本能率協会 主任講師
企業や大学等での講演・研修講師・コンサル・アドバイザーとしても活躍中。
サステナビリティ・ブランディング・コミュニケーション分野において豊富な経験を持ち、理論や実践手法のわかりやすい解説・指導法に定評がある。
※本文著作権は細田悦弘氏に所属します。