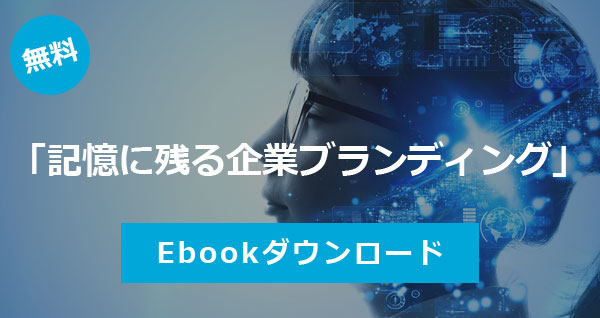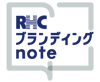ESGとは?注目のSDGsやCSR経営との関係を探る
SDGs

ESGとは?注目のSDGsやCSR経営との関係を探る
企業の評価指標として急速に認知が拡大した「ESG」。特に企業広報、IRに携わる方ならばもはや知らない方はいないでしょう。
今や「ESG」はマーケティングやリクルーティングにもかかわるようになってきました。
多くの企業人に関係する「ESG」とは、いったいどのようなものなのでしょうか。
ここでは最近よく聞くSDGsやCSR経営との関係性も含め、「ESG」というものについて以下に解説していきます。
今や「ESG」はマーケティングやリクルーティングにもかかわるようになってきました。
多くの企業人に関係する「ESG」とは、いったいどのようなものなのでしょうか。
ここでは最近よく聞くSDGsやCSR経営との関係性も含め、「ESG」というものについて以下に解説していきます。
ESGの基本的な意味とは
ESGとは3つの言葉の頭文字を取った略称です。
E(Environment=環境)、S(Social=社会)、G(Governance =ガバナンス)の頭文字を取って「ESG」としています。では、なぜこの3つが企業活動にとってそれほど大事なのでしょうか。
企業活動は比較評価をいつも必要としています。
なぜなら、その比較評価によって投資家がその企業に投資をすることになるからです。よく「企業の格付け」という言葉を耳にするでしょう。なぜ、企業は格付けされなければならないのか。それはとりもなおさず競争し勝ち残らなければ存在し続けることが出来ないからです。企業は選ばれなければ生き残れない存在であるとも言えます。
そしてこのESGこそ、新しい企業比較の目安となっているのです。かつての企業人にとっては、少々不思議に思えるところがあるかもしれません。企業はどれだけの利益を関係者にもたらすことができるのかが評価の基準であるべきだと思う人もいるでしょう。
しかし今、投資家たちの考え方は大きく変わっているのです。かつてのリーマンショックで得た教訓や、企業活動がもたらす地球環境への弊害、格差社会によって勃発する紛争、テロリズム、人口爆発などの致命的な課題。これらを放置した未来に、健全な経済活動は望めないことを知っているのです。
こうした理由から投資家たちは企業の通信簿に「ESG」を採用し始め、財務情報だけで評価することはせず、むしろ企業評価の8割を「ESG」で判断しようとしています。
簡単に言えば、売上げよりも環境と人にやさしく、不正な行いをしていないかどうかに投資判断の基準を置いているのです。そのうえで売り上げを上げている、あるいは売り上げが伸びている企業こそ、未来に生き残ると認識しているのです。
そして、それと足並みを揃えるように、社会も同じく様々な評価指標や約束事、公的機関への報告事項などが義務として整備され始めており、そうすることで健全な経済活動がいつまでも持続的に続くように導こうとする動きがあります。
それでは一体、どのような仕組みがESGを支え、この言葉をこれほど有名にしているのかを、次にご紹介していきましょう。
E(Environment=環境)、S(Social=社会)、G(Governance =ガバナンス)の頭文字を取って「ESG」としています。では、なぜこの3つが企業活動にとってそれほど大事なのでしょうか。
企業活動は比較評価をいつも必要としています。
なぜなら、その比較評価によって投資家がその企業に投資をすることになるからです。よく「企業の格付け」という言葉を耳にするでしょう。なぜ、企業は格付けされなければならないのか。それはとりもなおさず競争し勝ち残らなければ存在し続けることが出来ないからです。企業は選ばれなければ生き残れない存在であるとも言えます。
そしてこのESGこそ、新しい企業比較の目安となっているのです。かつての企業人にとっては、少々不思議に思えるところがあるかもしれません。企業はどれだけの利益を関係者にもたらすことができるのかが評価の基準であるべきだと思う人もいるでしょう。
しかし今、投資家たちの考え方は大きく変わっているのです。かつてのリーマンショックで得た教訓や、企業活動がもたらす地球環境への弊害、格差社会によって勃発する紛争、テロリズム、人口爆発などの致命的な課題。これらを放置した未来に、健全な経済活動は望めないことを知っているのです。
こうした理由から投資家たちは企業の通信簿に「ESG」を採用し始め、財務情報だけで評価することはせず、むしろ企業評価の8割を「ESG」で判断しようとしています。
簡単に言えば、売上げよりも環境と人にやさしく、不正な行いをしていないかどうかに投資判断の基準を置いているのです。そのうえで売り上げを上げている、あるいは売り上げが伸びている企業こそ、未来に生き残ると認識しているのです。
そして、それと足並みを揃えるように、社会も同じく様々な評価指標や約束事、公的機関への報告事項などが義務として整備され始めており、そうすることで健全な経済活動がいつまでも持続的に続くように導こうとする動きがあります。
それでは一体、どのような仕組みがESGを支え、この言葉をこれほど有名にしているのかを、次にご紹介していきましょう。
ESG投資とCSR経営の関係とは
前述のとおり、ESGとは企業の通信簿です。企業の通信簿を誰よりも一生懸命読む人とは誰でしょう。それは「投資家」に他なりません。
そのため、経営者は自社が如何にESGと真剣に向き合った企業であるかを投資家にアピールする努力をしいます。なぜならば企業はというのは「選ばれなければ生き残れない存在」だからです。
企業経営が急速にCSR(Corporate Social Responsibility=企業の社会的責任)経営に向かっているのは、シンプルに言えば“選ばれる企業”になるためかもしれません。しかし当然、選ばれたいからCSR経営をしている企業ばかりではありません。むしろ多くの企業は自らあることに気付き始めています。
それは自分たちの企業理念や事業の本質です。本来、自分たちの事業は社会に貢献し、持続的な成長を果たせるものであること、それを支える基本的な企業理念があることを再確認しています。そして、その基礎的な力こそが今後の社会において最もアピールすべきことであることに気付き始めています。
CSR経営は社会に貢献しながら、ステークホルダー(利害関係者)と共に持続的な成長が出来る企業の“底力”を経営の基盤とすることです。オプションの新規開発やボランティアではなく、いうなれば“底力”をどうすれば最大多数の幸福に結び付けられるか、にポイントを置いた経営方針であるといえます。そしてそれが今、投資家の目に留まっているわけです。
ESG投資は目先の華々しさより持続可能性があり、社会に貢献する企業に投資しようという、いわば“選手宣誓”を行っている人たちによる投資です。具体的にはこれを「PRI」と言います。
実を言うと、投資家の最大手である機関投資家の多くは、すでに「PRI」という選手宣誓に署名して投資活動を行っています。PRIについては後ほど詳しく紹介しますが、PRIに署名した機関投資家たちの行う「ESG投資」も、年を追うごとに良好な結果を示しているため、個人投資家たちからも注目を集めているというわけです。「ESG投資」が急速に注目を集めているのは、それによって投資家たちが利益を得ているからに他なりません。
そしてつい最近、わが国でもそのことを象徴する動きが見られました。2020年10月に民間最大手の機関投資家である日本生命が、今後の全投資にESG指標を採用すると明言したのです。また、すでに世界最大の機関投資家である我が国の年金機構=GPIFは、PRIに則った投資を行うことを2015年に明言しています。
ESG投資を投資の大原則とする投資家が増え続けているからこそ、企業はCSR経営を中心とする企業活動を始めているのです。そして、それは相対的な企業評価につながっています。CSR経営を行うか否か、というシンプルな差異に繋がるからです。
そのため、経営者は自社が如何にESGと真剣に向き合った企業であるかを投資家にアピールする努力をしいます。なぜならば企業はというのは「選ばれなければ生き残れない存在」だからです。
企業経営が急速にCSR(Corporate Social Responsibility=企業の社会的責任)経営に向かっているのは、シンプルに言えば“選ばれる企業”になるためかもしれません。しかし当然、選ばれたいからCSR経営をしている企業ばかりではありません。むしろ多くの企業は自らあることに気付き始めています。
それは自分たちの企業理念や事業の本質です。本来、自分たちの事業は社会に貢献し、持続的な成長を果たせるものであること、それを支える基本的な企業理念があることを再確認しています。そして、その基礎的な力こそが今後の社会において最もアピールすべきことであることに気付き始めています。
CSR経営は社会に貢献しながら、ステークホルダー(利害関係者)と共に持続的な成長が出来る企業の“底力”を経営の基盤とすることです。オプションの新規開発やボランティアではなく、いうなれば“底力”をどうすれば最大多数の幸福に結び付けられるか、にポイントを置いた経営方針であるといえます。そしてそれが今、投資家の目に留まっているわけです。
ESG投資は目先の華々しさより持続可能性があり、社会に貢献する企業に投資しようという、いわば“選手宣誓”を行っている人たちによる投資です。具体的にはこれを「PRI」と言います。
実を言うと、投資家の最大手である機関投資家の多くは、すでに「PRI」という選手宣誓に署名して投資活動を行っています。PRIについては後ほど詳しく紹介しますが、PRIに署名した機関投資家たちの行う「ESG投資」も、年を追うごとに良好な結果を示しているため、個人投資家たちからも注目を集めているというわけです。「ESG投資」が急速に注目を集めているのは、それによって投資家たちが利益を得ているからに他なりません。
そしてつい最近、わが国でもそのことを象徴する動きが見られました。2020年10月に民間最大手の機関投資家である日本生命が、今後の全投資にESG指標を採用すると明言したのです。また、すでに世界最大の機関投資家である我が国の年金機構=GPIFは、PRIに則った投資を行うことを2015年に明言しています。
ESG投資を投資の大原則とする投資家が増え続けているからこそ、企業はCSR経営を中心とする企業活動を始めているのです。そして、それは相対的な企業評価につながっています。CSR経営を行うか否か、というシンプルな差異に繋がるからです。
ESGとSDGsの密接な関係をPDCAで考える
ところでESGが企業の通知表であるなら、その通知表だけ真剣に整備し投資家に対して報告し続ければ、それを実行した企業は“選ばれる”のでしょうか。いや、そもそもどうすれば競合他社より高い点数を通知表で得られるのでしょうか。
実は前述のGPIF(年金機構)がその答えを一部示唆しています。
簡単に言えば「GPIFはPRIに則り責任投資をするから、企業はSDGsを達成することで競合他社との競争優位性を実現してほしい」と発言しているのです。
E(Environment=環境)、S(Social=社会)、G(Governance =ガバナンス)の各指標で投資するかしないかを判断する、と言っているのに、SDGsの達成を目指せとはどういうことなのでしょう。
ESG投資は企業の本質に対して評価し、投資するものであることは前述のとおりです。しかし、その評価は現在の実力と、これからの未来に対する期待についても対象となります。
つまり企業がこれから先、何をする気でどうやって社会に貢献し、持続可能な企業活動を実現していくつもりなのかを宣言することも評価の対象となるわけです。
さて、ビジネスの過程においてPDCAサークルという言葉を聞いたことがない人はかなり少ないでしょう。念のために申し上げるとP(Plan)→D(do)→C(check)→A(action)の事です。SDGsとESGの関係はまさにこのPDCAサークルで説明できます。
企業は企業活動を通じて、「環境と人にやさしく、不正な行いをしない」ための目標を立てます。その目標(ゴール)となるものがSDGsです。なぜSDGsを目標として採用するかというと、投資家の目にも一目瞭然で企業比較が出来るからです。
SDGsはもはや義務教育を受ける小学生でも理解している基礎知識となりつつありますので、企業は誰もが知る共通の目標をP(Plan)することによって達成しようとしている目標を社会に知らしめることが出来ます。
P(Plan)の次に企業が行うのはD(do)です。言うだけでなく実行するからこそ評価されるわけです。例えば二酸化炭素の排出をこれだけ減らしたとか、これだけの女性を役員に登用したとか。
このD(do)をC(check)するための指標が「ESG」です。企業の通知表にはSDGsにより計画し実行された結果が「ESG」として見える化されます。
これを受けた投資家は投資=A(action)します。コンシューマー(消費者)は商品を買います。そして、採用応募者はエントリーをするわけです。
さらに、GPIFは「SDGsを使って競合他社に比べて競争優位を実現することを推奨する」としています。つまり、SDGsを達成しようとしていることを他社との差別化に使い、SDGsの達成に向けて競い合うことを推奨するとしているのです。
ESGの評価を他社より高めるということは,SDGsのP(Plan)→D(do)を絶え間なく行うことにより成果を上げ続ける、ということになるでしょう。
実は前述のGPIF(年金機構)がその答えを一部示唆しています。
簡単に言えば「GPIFはPRIに則り責任投資をするから、企業はSDGsを達成することで競合他社との競争優位性を実現してほしい」と発言しているのです。
E(Environment=環境)、S(Social=社会)、G(Governance =ガバナンス)の各指標で投資するかしないかを判断する、と言っているのに、SDGsの達成を目指せとはどういうことなのでしょう。
ESG投資は企業の本質に対して評価し、投資するものであることは前述のとおりです。しかし、その評価は現在の実力と、これからの未来に対する期待についても対象となります。
つまり企業がこれから先、何をする気でどうやって社会に貢献し、持続可能な企業活動を実現していくつもりなのかを宣言することも評価の対象となるわけです。
さて、ビジネスの過程においてPDCAサークルという言葉を聞いたことがない人はかなり少ないでしょう。念のために申し上げるとP(Plan)→D(do)→C(check)→A(action)の事です。SDGsとESGの関係はまさにこのPDCAサークルで説明できます。
企業は企業活動を通じて、「環境と人にやさしく、不正な行いをしない」ための目標を立てます。その目標(ゴール)となるものがSDGsです。なぜSDGsを目標として採用するかというと、投資家の目にも一目瞭然で企業比較が出来るからです。
SDGsはもはや義務教育を受ける小学生でも理解している基礎知識となりつつありますので、企業は誰もが知る共通の目標をP(Plan)することによって達成しようとしている目標を社会に知らしめることが出来ます。
P(Plan)の次に企業が行うのはD(do)です。言うだけでなく実行するからこそ評価されるわけです。例えば二酸化炭素の排出をこれだけ減らしたとか、これだけの女性を役員に登用したとか。
このD(do)をC(check)するための指標が「ESG」です。企業の通知表にはSDGsにより計画し実行された結果が「ESG」として見える化されます。
これを受けた投資家は投資=A(action)します。コンシューマー(消費者)は商品を買います。そして、採用応募者はエントリーをするわけです。
さらに、GPIFは「SDGsを使って競合他社に比べて競争優位を実現することを推奨する」としています。つまり、SDGsを達成しようとしていることを他社との差別化に使い、SDGsの達成に向けて競い合うことを推奨するとしているのです。
ESGの評価を他社より高めるということは,SDGsのP(Plan)→D(do)を絶え間なく行うことにより成果を上げ続ける、ということになるでしょう。
ESGがここまで重要になってきた歴史的背景
さて、ESGがこれほど重要な指標として認知されるまでには、歴史的な背景がありました。これまでの投資や消費者の消費行動は、ESGを意識したものとは違う次元にあったのかもしれません。
言い過ぎかもしれませんが、今までの投資や消費行動の前提にあるものは、「地球の恩恵は無尽蔵にある」という勘違いと「他人と比べも少しでも幸せになることが大事」という考え方ではなかったでしょうか。これこそが資本主義の根底にあったものかもしれません。
実はこの考え方の大きな転換点となったのが、リーマンショックだったといわれています。リーマンショックで世界の経済が危機に陥った時に、投資家たちは企業の本質を見極めて責任ある投資をしようとお互いに合意しました。ご存じの方も多いと思いますが、これを「スチュワートシップコード」といいます。
後述するPRIは、このスチュワートシップコードより前に国連が定めた投資原則ですが、この時点ではPRIの存在はまだ希薄でした。
しかし、リーマンショックの影響で投資家たちは企業の持続可能性に着目しました。その後、気候変動や資源の枯渇、人口爆発やテロリズムの横行など、私たちの価値観を変える状況が次々に顕在化し始めました。
わが国でESGの意識が急激に広まったのは、2015年にGPIFがPRIに加盟することを宣言した時に違いありません。そこで日本の企業は初めてESGやSDGsを意識するようになったのです。
それ以降も地球全体が抱える課題は好転の兆しがなく悪化の一歩をたどっていました。
そこに今回の新型コロナウィルスという地球規模の大問題が発生したのです。新型コロナウィルスの発生も、実は気候変動や資源の枯渇に起因する問題といわれているため、企業はますますSDGs・ESGへの貢献を問われる形となっているのです。
では、これから未来はどうなるでしょう。専門家によれば今後の気候変動リスクが突然なくなるという見込みはかなり低いようです。資源の枯渇も深刻さを増し、人口爆発も右肩上がりであることに変わりはありません。
世界全体が危機にさらされるたび、意識が変わってきた証が「ESG」であるとするなら、これから先に企業の評価基準が大きく変わることは、おそらくないでしょう。
PRIによる責任投資原則に批准し続ける機関投資家たちは年々増え続け、2020年の総資産額は103兆ドルにまで達しています。
言い過ぎかもしれませんが、今までの投資や消費行動の前提にあるものは、「地球の恩恵は無尽蔵にある」という勘違いと「他人と比べも少しでも幸せになることが大事」という考え方ではなかったでしょうか。これこそが資本主義の根底にあったものかもしれません。
実はこの考え方の大きな転換点となったのが、リーマンショックだったといわれています。リーマンショックで世界の経済が危機に陥った時に、投資家たちは企業の本質を見極めて責任ある投資をしようとお互いに合意しました。ご存じの方も多いと思いますが、これを「スチュワートシップコード」といいます。
後述するPRIは、このスチュワートシップコードより前に国連が定めた投資原則ですが、この時点ではPRIの存在はまだ希薄でした。
しかし、リーマンショックの影響で投資家たちは企業の持続可能性に着目しました。その後、気候変動や資源の枯渇、人口爆発やテロリズムの横行など、私たちの価値観を変える状況が次々に顕在化し始めました。
わが国でESGの意識が急激に広まったのは、2015年にGPIFがPRIに加盟することを宣言した時に違いありません。そこで日本の企業は初めてESGやSDGsを意識するようになったのです。
それ以降も地球全体が抱える課題は好転の兆しがなく悪化の一歩をたどっていました。
そこに今回の新型コロナウィルスという地球規模の大問題が発生したのです。新型コロナウィルスの発生も、実は気候変動や資源の枯渇に起因する問題といわれているため、企業はますますSDGs・ESGへの貢献を問われる形となっているのです。
では、これから未来はどうなるでしょう。専門家によれば今後の気候変動リスクが突然なくなるという見込みはかなり低いようです。資源の枯渇も深刻さを増し、人口爆発も右肩上がりであることに変わりはありません。
世界全体が危機にさらされるたび、意識が変わってきた証が「ESG」であるとするなら、これから先に企業の評価基準が大きく変わることは、おそらくないでしょう。
PRIによる責任投資原則に批准し続ける機関投資家たちは年々増え続け、2020年の総資産額は103兆ドルにまで達しています。
ESGとGPIFおよびPRIの関係
ESGが急速に普及したきっかけは「見える化」が進んだことだといえるでしょう。漠然と環境・社会・ガバナンスに貢献していると表現するだけでは済まなくなってきたからこそ、ESGが注目される企業指標となったに違いありません。
日本におけるESG普及のスタートラインは、前述の通り「GPIFによるPRIへの署名」です。GPIFは世界最大の機関投資家、我が国の年金機構「年金積立金管理運用独立行政法人」です。すなわち企業に対し投資をしている最も大きな巨人なのです。
では“PRI”とは何でしょうか。PRIは日本語で「責任投資原則」といって、国連が2005年に宣言した投資原則であり、俗にいう“ならず者投資家”にはならないという選手宣誓です。責任ある投資を行うことで社会に利益をもたらすという考え方ととらえても良いでしょう。
また、PRIは何もGPIFだけが署名しているのではありません。2020年現在で3038にも上る機関投資家が署名をしており、その総運用資産額は103.4兆ドルにのぼります。それだけ多くの投資家がESGを基準に企業を評価し、投資対象を決めると宣言しているのです。
話をGPIFに戻します。PRIに署名したGPIFは、どうやって責任投資原則に則り投資を行うかを具体的に示しています。それがGPIFによって採用されている「4つのESG投資指数」です。
具体的には
「FTSE Blossom Japan Index」
「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数」
「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」
「MSCI 日本株女性活躍指数(WIN)」
の4つになります。なお、これはGPIF特有の投資判断の基準です。
これらの指数を総合評価して投資判断をするとしているため、各企業は必死にこれらの指数が上がるための努力を行い、それを様々な評価機関に報告しているのです。それはGPIFに投資してもらうための努力であるといえます。そして、そのESG指標をより良い数値にするための行動こそが「SDGsの達成」になるわけです。
しかし、PRIに署名したすべての機関投資家がGPIFと同じ投資基準を設定しているわけではありません。世界的にポピュラーな評価基準は「FTSE4Good Index Series」だといわれています。
FTSE4Good Indexは、世界主要企業約3000社を対象とするESG評価に基づいて発表されています。その評価は透明性を保つために企業からの情報提供ではなく、一般に公表されている情報のみを用いて実施しているとされます。300以上の項目があり、「気候変動」「水」「生物多様性」「汚染・資源」「健康・安全性」「労働基準」「人権・コミュニティ」「消費者責任」「腐敗防止」「納税透明性」「リスクマネジメント」「コーポレートガバナンス」などを評価します。
これがPRIに署名した投資家たちの評価基準であり姿勢なのです。
もちろん世の中の投資家全てがPRIに署名しているわけではありませんが、署名機関の数や総運用資産額も驚異的に増大しているのが現状です。
そのため、企業の評価がESG評価に偏重しているのです。
日本におけるESG普及のスタートラインは、前述の通り「GPIFによるPRIへの署名」です。GPIFは世界最大の機関投資家、我が国の年金機構「年金積立金管理運用独立行政法人」です。すなわち企業に対し投資をしている最も大きな巨人なのです。
では“PRI”とは何でしょうか。PRIは日本語で「責任投資原則」といって、国連が2005年に宣言した投資原則であり、俗にいう“ならず者投資家”にはならないという選手宣誓です。責任ある投資を行うことで社会に利益をもたらすという考え方ととらえても良いでしょう。
また、PRIは何もGPIFだけが署名しているのではありません。2020年現在で3038にも上る機関投資家が署名をしており、その総運用資産額は103.4兆ドルにのぼります。それだけ多くの投資家がESGを基準に企業を評価し、投資対象を決めると宣言しているのです。
話をGPIFに戻します。PRIに署名したGPIFは、どうやって責任投資原則に則り投資を行うかを具体的に示しています。それがGPIFによって採用されている「4つのESG投資指数」です。
具体的には
「FTSE Blossom Japan Index」
「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数」
「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」
「MSCI 日本株女性活躍指数(WIN)」
の4つになります。なお、これはGPIF特有の投資判断の基準です。
これらの指数を総合評価して投資判断をするとしているため、各企業は必死にこれらの指数が上がるための努力を行い、それを様々な評価機関に報告しているのです。それはGPIFに投資してもらうための努力であるといえます。そして、そのESG指標をより良い数値にするための行動こそが「SDGsの達成」になるわけです。
しかし、PRIに署名したすべての機関投資家がGPIFと同じ投資基準を設定しているわけではありません。世界的にポピュラーな評価基準は「FTSE4Good Index Series」だといわれています。
FTSE4Good Indexは、世界主要企業約3000社を対象とするESG評価に基づいて発表されています。その評価は透明性を保つために企業からの情報提供ではなく、一般に公表されている情報のみを用いて実施しているとされます。300以上の項目があり、「気候変動」「水」「生物多様性」「汚染・資源」「健康・安全性」「労働基準」「人権・コミュニティ」「消費者責任」「腐敗防止」「納税透明性」「リスクマネジメント」「コーポレートガバナンス」などを評価します。
これがPRIに署名した投資家たちの評価基準であり姿勢なのです。
もちろん世の中の投資家全てがPRIに署名しているわけではありませんが、署名機関の数や総運用資産額も驚異的に増大しているのが現状です。
そのため、企業の評価がESG評価に偏重しているのです。
ESGに関係する評価機関とは
投資家はGPIFと同様に評価機関が発表する“企業の点数=インデックス”を目安にしてESG投資をしているので、企業は様々な評価機関に対し報告をしています。FTESは透明性を保つために企業からの情報提供ではなく、一般に公表されている情報を用いて評価を実施していると言っていますが、例えば以下のような様々な機関に対して情報を公開することで企業の点数=インデックス”が作成されます。
・CDP
CDPは気候変動などの環境分野に取り組む国際NGOで、2000年に設立されたプロジェクト「カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト」がその前身となっています。機関投資家が関心を持つ気候変動関連の情報を収集、開示することに焦点を絞り、世界の主要企業が排出する二酸化炭素の量や気候変動への取り組みを行っています。
・TCFD
気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)の頭文字を取った略称です。G20の要請を受け、金融安定理事会(FSB)により設立されました。企業等に対し、気候変動関連リスク、及び機会に関する下記の項目について開示することを推奨しています。
ガバナンス(Governance):どのような体制で検討して企業経営に反映しているか。
戦略(Strategy):短期・中期・長期にわたり、企業経営にどのように影響を与えるか。
リスク管理(Risk Management):どのように特定、低減しようとしているか。
指標と目標(Metrics and Targets):どのような指標を用いて判断し、評価しているか。
・MSCI
モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナルの略称で、米国を拠点としています。投資家向けに株価指数(インデックス)や債券指数などを算出しています。例としてはGPIFが採用している「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」「MSCI 日本株女性活躍指数(WIN)」などがあります。
・FTSE
英国を拠点に事業を展開し、投資家向けに株価指数(インデックス)や債券指数などを算出しています。FTSE Russellはその商標です。世界的にポピュラーな評価基準「FTSE4Good Index Series」を算出しています。GPIFでは「FTSE Blossom Japan Index」を採用しています。
・CDP
CDPは気候変動などの環境分野に取り組む国際NGOで、2000年に設立されたプロジェクト「カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト」がその前身となっています。機関投資家が関心を持つ気候変動関連の情報を収集、開示することに焦点を絞り、世界の主要企業が排出する二酸化炭素の量や気候変動への取り組みを行っています。
・TCFD
気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)の頭文字を取った略称です。G20の要請を受け、金融安定理事会(FSB)により設立されました。企業等に対し、気候変動関連リスク、及び機会に関する下記の項目について開示することを推奨しています。
ガバナンス(Governance):どのような体制で検討して企業経営に反映しているか。
戦略(Strategy):短期・中期・長期にわたり、企業経営にどのように影響を与えるか。
リスク管理(Risk Management):どのように特定、低減しようとしているか。
指標と目標(Metrics and Targets):どのような指標を用いて判断し、評価しているか。
・MSCI
モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナルの略称で、米国を拠点としています。投資家向けに株価指数(インデックス)や債券指数などを算出しています。例としてはGPIFが採用している「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」「MSCI 日本株女性活躍指数(WIN)」などがあります。
・FTSE
英国を拠点に事業を展開し、投資家向けに株価指数(インデックス)や債券指数などを算出しています。FTSE Russellはその商標です。世界的にポピュラーな評価基準「FTSE4Good Index Series」を算出しています。GPIFでは「FTSE Blossom Japan Index」を採用しています。
ESG投資の分類
世界のESG投資額の統計を集計している国際団体のGSIA(Global Sustainable Investment Alliance)はESG投資を以下の7つに分類しています。これらはいずれも責任投資原則に則った投資であると考えられます。
1. ネガティブスクリーニング
ESG投資の対象として基準を満たさない企業を排除すること。武器製造企業、原子力発電企業、児童就労を強いる企業などに適用されます。
2. ポジティブスクリーニング
従業員政策、環境保護、人権などの社会問題や環境問題でリーダーシップを発揮している企業に投資すること。
3. 規範に基づくスクリーニング
ESG分野での国際基準に照らし合わせ、その基準をクリアしていない企業を投資先のリストから除外する方法。2000年に発足した「国連グローバル・コンパクト」に賛同しているか否かなどが指針となります。
4. ESG統合型
投資選定の過程で従来考慮してきた財務情報だけでなく、非財務情報も含めて分析をする手法。ここでの非財務情報とは、E(環境)、S(社会)、G(企業統治)のこと。
5. サステナビリティ・テーマ投資型
サスビリティ(持続可能性)を全面に謳ったファンドへの投資。特に再生可能エネルギー、持続可能な農業等に関する投資が有名です。
6. インパクト投資型
社会・環境に貢献する技術やサービスを提供する企業に対して行う投資。社会的に望ましい成果をもたらす製品やサービスを提供する企業の銘柄が集まっています。
7. エンゲージメント・議決権行使型
株主として企業に対してESGに関する案件の積極的な働きかけを行う投資手法。いわゆる「アクティビスト(物言う株主)」型の戦略。
1. ネガティブスクリーニング
ESG投資の対象として基準を満たさない企業を排除すること。武器製造企業、原子力発電企業、児童就労を強いる企業などに適用されます。
2. ポジティブスクリーニング
従業員政策、環境保護、人権などの社会問題や環境問題でリーダーシップを発揮している企業に投資すること。
3. 規範に基づくスクリーニング
ESG分野での国際基準に照らし合わせ、その基準をクリアしていない企業を投資先のリストから除外する方法。2000年に発足した「国連グローバル・コンパクト」に賛同しているか否かなどが指針となります。
4. ESG統合型
投資選定の過程で従来考慮してきた財務情報だけでなく、非財務情報も含めて分析をする手法。ここでの非財務情報とは、E(環境)、S(社会)、G(企業統治)のこと。
5. サステナビリティ・テーマ投資型
サスビリティ(持続可能性)を全面に謳ったファンドへの投資。特に再生可能エネルギー、持続可能な農業等に関する投資が有名です。
6. インパクト投資型
社会・環境に貢献する技術やサービスを提供する企業に対して行う投資。社会的に望ましい成果をもたらす製品やサービスを提供する企業の銘柄が集まっています。
7. エンゲージメント・議決権行使型
株主として企業に対してESGに関する案件の積極的な働きかけを行う投資手法。いわゆる「アクティビスト(物言う株主)」型の戦略。
ESGにより企業は競争優位性を獲得する
以上のように企業は「透明性」の中で真摯にSDGsを定めて実行し、評価機関の評価を得て企業としての点数を上げることで「選ばれる企業」になるわけです。GPIFをはじめとしたPRI署名済の機関投資家たちは、そうすることによって企業間競争に勝ってほしいと述べています。
これは「ならず者投資家が投資するならず者企業が減ってほしい。そうすることで“ソーシャルグッド”に溢れる世界になる。」と言っているのと同義です。ソーシャルグッド(Social Good)とは、地球環境や地域コミュニティなどの「社会」に対して良いインパクトを与える活動や製品、サービスの総称を指します。
この傾向が今後も続けば、「ESG企業」と「非ESG企業」が二分することは容易に想像できます。そして今後、地球温暖化や人口爆発や資源の枯渇が、ある日突然なかったことになる日は来そうにありません。
そのため、「ESG企業」と認定されることは競争優位性を獲得する上で非常に重要です。
そして、そこに向けて努力しているSDGs達成のためのすべての行動は、企業にとって競合他社との比較競争上、最大のプロモーションとなりうるのです。
これは「ならず者投資家が投資するならず者企業が減ってほしい。そうすることで“ソーシャルグッド”に溢れる世界になる。」と言っているのと同義です。ソーシャルグッド(Social Good)とは、地球環境や地域コミュニティなどの「社会」に対して良いインパクトを与える活動や製品、サービスの総称を指します。
この傾向が今後も続けば、「ESG企業」と「非ESG企業」が二分することは容易に想像できます。そして今後、地球温暖化や人口爆発や資源の枯渇が、ある日突然なかったことになる日は来そうにありません。
そのため、「ESG企業」と認定されることは競争優位性を獲得する上で非常に重要です。
そして、そこに向けて努力しているSDGs達成のためのすべての行動は、企業にとって競合他社との比較競争上、最大のプロモーションとなりうるのです。
ライタープロフィール

神澤 肇(カンザワ ハジメ)
リボンハーツクリエイティブ株式会社 代表取締役社長
創業40年以上の制作会社リボンハーツクリエイティブ(RHC)代表。
企業にコンテンツマーケティングを提供し始めて約15年。
数十社の大手企業オウンドメディアの企画・制作・運用を担当。
WEBを使用した企業ブランディングのプロフェッショナル。
映像業界出身で、WEB、紙媒体とクロスメディアでの施策を得意とする。
趣味はカメラとテニス、美術館巡り、JAZZ好き。