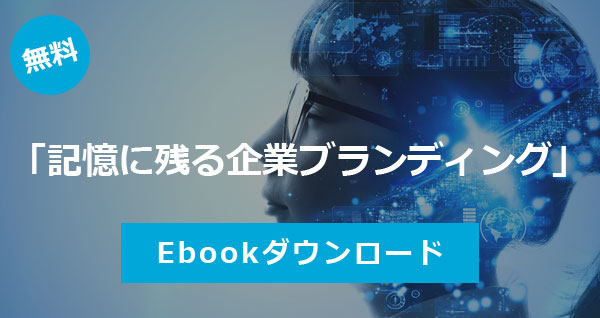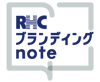ブランドエクイティ概念に関する歴史と、そのマネジメント
ブランディング

「ブランドエクイティ」は、その呼び名のとおりブランドをエクイティ(資産)ととらえる視点で考察、マネジメントする手法のことです。当コラム「ブランディングnote」でもこれまで、
■ブランドエクイティとは 形のないブランドを資産として定義
■ブランドエクイティを測定する方法
の記事でトピックとして採りあげ、解説しました。
今回の記事ではさらにわが国におけるブランドエクイティ概念に関する歴史と、そのマネジメントについて簡単に述べていこうと思います。
わが国における「ブランドエクイティ」概念の歴史
ブランドエクイティという用語が一般に浸透した背景には、1994年1月にダイヤモンド社から刊行されたD.A.アーカーの「ブランド・エクイティ戦略」が大きく影響しています。
それまでもブランドという概念は、マーケティングの世界に存在していました。しかしそれらはまだ体系的にまとめられておらず、商品政策ノウハウや、海外有名ブランドの事例紹介といった次元、また1991年の商標法改正に伴う導入を背景とした差別化戦略など、個別の論にとどまっていました。
アーカーの論考を嚆矢としてブランド論への注目度は急速に高まり、大学研究者を中心に続々と論文・著作が世に問われるようになります。ビジネスの現場では主として広告会社主導でエクイティの強化、価値向上に向けた提案が活発になっていきました。
アーカーの著作はアメリカにおける膨大な事例研究を背景に、ブランドの創造と管理の手法を詳細に分析、体系的に整理した点で画期的なものでした。また続編というべき「Building Strong Brands」(邦題:ブランド優位の戦略)では、ブランド・アイデンティティを軸に論を発展させ、エクイティの測定についても10項目の尺度を示すなどより具体的な試みがなされています。
アーカーのブランドエクイティ論は、企業やブランドを発信する側に立って考察する立場をとっています。一方、ブランドというものが顧客の脳内でどのように印象化され、エクイティとしての価値を持つようになるのか、という視座に注目したのが、アーカーと並び称されるダートマス大学教授のK.L.ケラーです。
ケラーのブランドエクイティ論も、アーカー同様に日本の経営者やマーケター、研究者に大きな影響を与えました。ただ、どちらもアメリカ国内とグローバル市場を対象とした研究に基づくものであるため、
■紹介されている事例がフォードやバセリン、ビーキンズ、シアーズなど日本の消費者になじみが薄く、ピンとこない
■翻訳の訳文・訳語が堅く、言い回しが分かりにくい
■GMの戦略車ブランド「サターン」のように、今となっては失敗とみなされている事例が、成功例として紹介されている
などの難点がありました。
その後、日本におけるブランド論議はエクイティからCIを含むアイデンティティの領域、評価・育成・診断方法、広告展開、インベスター・リレーションなどさまざまな方面に拡張されていき、年に数十もの論文や書籍が発表される百家争鳴の時代を迎えます。ところが日本経済の低迷と共にいつしか沈静化し、書名に「ブランド」を冠した新刊も数えるほどに減少していきました。
そして再び、2010年代あたりから注目すべき経営テーマとして復活、〜ingを付与した「ブランディング」として注目されるようになります。
その背景には、
■SDGsやサステナブルなどかつてはビジネスに向かないとされていた領域が、企業経営にかかわる重要な要素として浮上してきたこと
■労働や雇用の概念が変容し、優秀な人材確保の必要性が増大したこと
■人材の流動化に伴い、ブランドの管理が有視界飛行からデータ化・システム化の傾向を強めたこと
■情報技術と環境の充実化によりコミュニケーションコストが低下し、個人や中小組織、スタートアップでもブランドを構築できる可能性が増大したこと
があります。
デジタル時代のブランドエクイティ
ブランドエクイティはアセットの一つとして、本来的には財務的に評価、資産計上できるポテンシャルを
持つものです。しかし、その会計基準はなかなか設計しづらいものがあり、いまだその価値を数値化する手法は、1994年にアーカーが示した域を越えていません。
ただし、不動産や有価証券など他の有形・無形資産と同様に、その価値が内部環境・外部環境の要因から下落し、負債化するリスクを持つものである点に、注意が必要です。ブランドプロミス(前編・後編)のコラムでも解説していますが、築き上げてきたブランドが広く知られたものであり、その価値が大きいほど、不祥事や失策により傷ついた場合の代償が大きなものとなります。インターネットメディアが多様化したことで、SNSですぐに情報が拡散されたり、隠していた事実が一般ユーザーによって暴露されたりするケースも非常に多くなりました。
またデジタルマーケティング手法の発展は、Googleアナリティクスなどを通じたデータの取得と参照を民主化し、容易なものにしています。このことが商品やブランドのコミュニケーションの視座を短期的なサイクルに矮小化し、ブランド全体をより統合的・計画的に管理することを、逆に困難にしている面もあります。
デジタル時代にあっても、進化する技術を手段・手法として活用しながら、顧客をはじめとする対象者との結びつきを地道に、丹念に強化していく態度がエクイティの維持と向上に貢献すると言えるでしょう。
ライタープロフィール

神澤 肇(カンザワ ハジメ)
リボンハーツクリエイティブ株式会社 代表取締役社長
創業40年以上の制作会社リボンハーツクリエイティブ(RHC)代表。
企業にコンテンツマーケティングを提供し始めて約15年。
数十社の大手企業オウンドメディアの企画・制作・運用を担当。
WEBを使用した企業ブランディングのプロフェッショナル。
映像業界出身で、WEB、紙媒体とクロスメディアでの施策を得意とする。
趣味はカメラとテニス、美術館巡り、JAZZ好き。