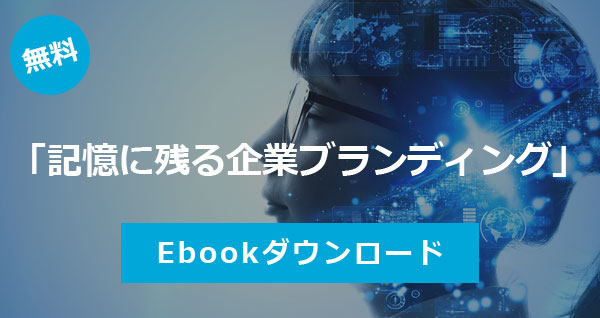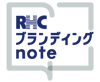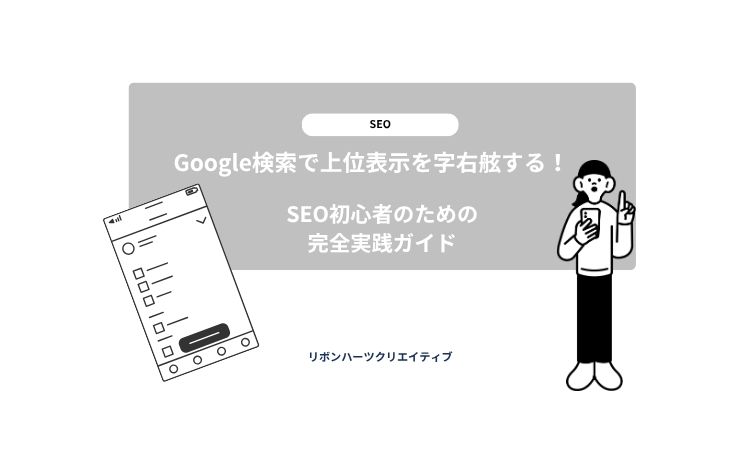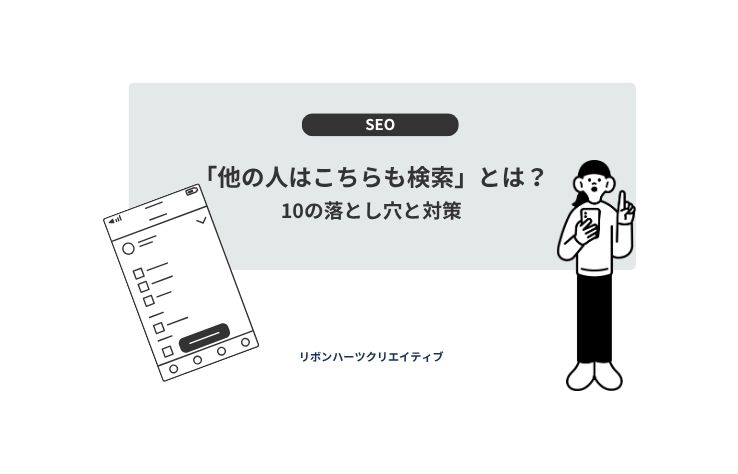成果を生む企業オウンドメディアの作り方:戦略設計から外注活用まで完全ガイド
コンテンツマーケティング
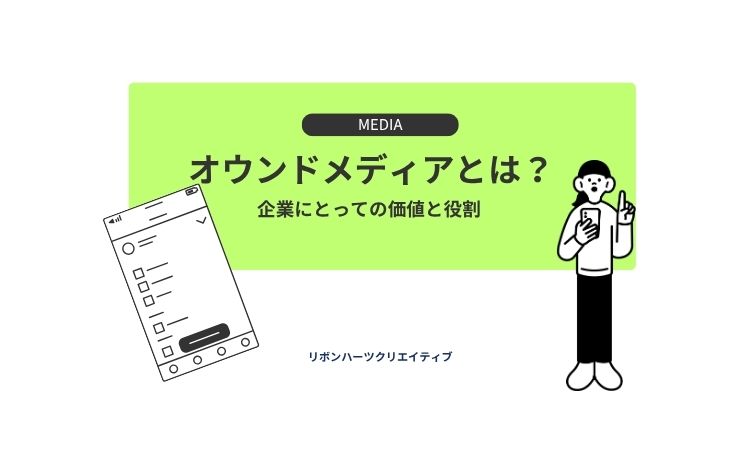
広告に頼らず、自社の価値を発信する手段として注目されている「オウンドメディア」。採用やブランディングを支える戦略的ツールとして、多くの企業が導入を進めています。本記事ではその基本から実践までを解説します。
オウンドメディアとは?企業にとっての価値と役割
オウンドメディアとは、自社が運営・管理する情報発信の場です。自社サイトやブログ、メールマガジン、SNSなどが該当し、発信するコンテンツも自由に設計できます。
従来のように広告に頼らず、顧客との信頼関係を築く手段として、多くの企業が導入を進めています。
広告依存からの脱却──企業オウンドメディアが注目される理由
近年、広告のクリック率や信頼性が低下し、従来型のマーケティングでは成果が出にくくなっています。こうした背景から、自社の価値や世界観を伝えられるオウンドメディアの重要性が高まっています。
制作したコンテンツは資産となり、検索やSNS経由で継続的にユーザーと接点を持てます。広告費をかけずに集客やブランディングができる点も、大きな魅力です。
企業ブランディングと採用活動を支える基盤に
オウンドメディアは、商品やサービスの紹介だけでなく、企業の理念や働き方、社員の声などを発信する場としても活用されます。
これにより企業文化への共感が生まれ、採用活動にも効果を発揮します。特に若年層の求職者は、給与や福利厚生だけでなく「どんな人が働いているか」「社風は自分に合うか」といった点を重視しており、リアルな情報発信が重要です。
継続的な発信は企業の信頼性や専門性を高め、他社との差別化にもつながります。今やオウンドメディアは、企業の広報・採用の要といえる存在です。
成功するオウンドメディア戦略の立て方
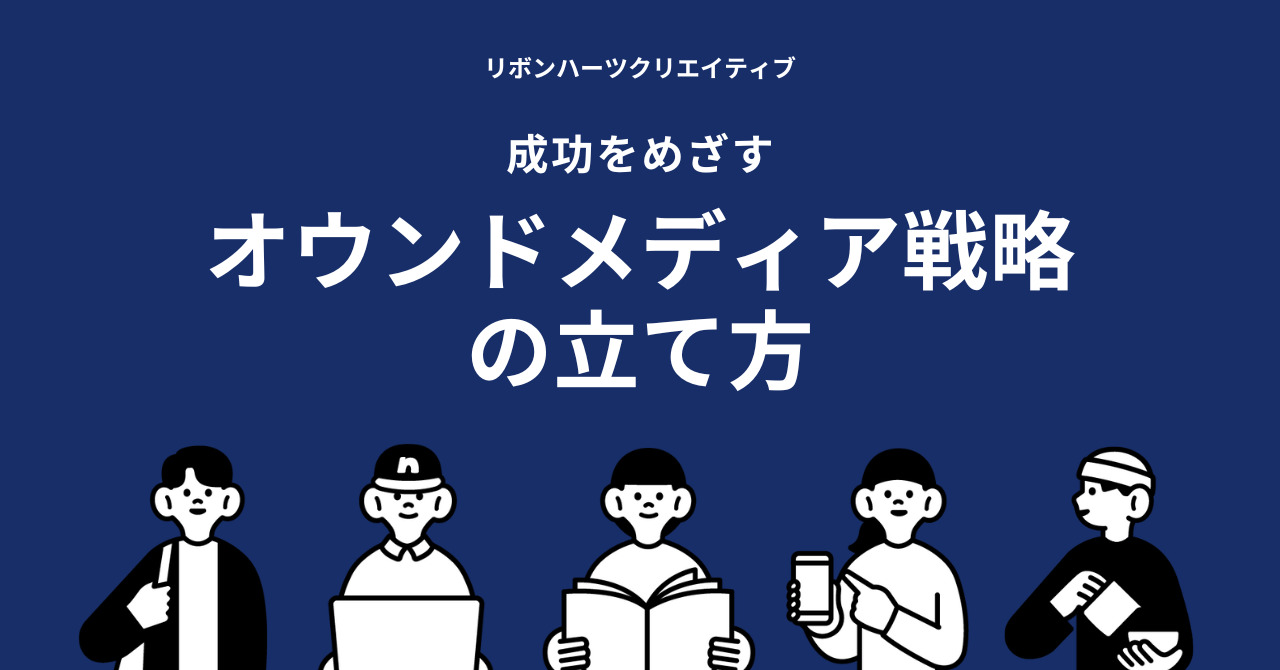
オウンドメディアを立ち上げるだけでは成果は得られません。目的・ターゲット・運用体制を明確にしたうえで、戦略的に運営することが鍵です。ここでは、成功につながる3つの戦略的視点を紹介します。
目的設定がすべてを決める──集客・採用・PRの違い
オウンドメディアの戦略設計で最初にすべきことは「目的の明確化」です。集客を狙うのか、採用強化か、企業の認知度向上かによって、コンテンツの内容や配信方法が大きく変わります。
たとえば集客目的ならSEO対策を中心に記事コンテンツを強化し、採用なら社員インタビューや社風紹介が有効です。目的があいまいなまま進めると、成果につながりにくいため注意が必要です。
ターゲットの明確化とペルソナ設計
成果を上げるには、「誰に何を伝えるか」を明確にすることが欠かせません。具体的なターゲット像=ペルソナを設計することで、読者に響くコンテンツを作りやすくなります。
性別・年齢・職業・悩み・情報収集の手段などを詳細にイメージすることで、発信内容に一貫性が生まれ、ユーザーとの接点も強固になります。
運用体制・KPI設計のポイント
オウンドメディアは継続的な運用が前提であり、社内での役割分担、編集・公開フローの整備が不可欠となります。加えて、成果を測るためにはKPI(重要業績評価指標)を明確に定める必要があります。
PV(ページビュー)やCV(問い合わせ・応募など)を設定し、定期的に進捗を見直すことで、改善と成長につながるでしょう。
ゼロから始めるオウンドメディアの構築ステップ
戦略を練った後は、実際の構築フェーズに入ります。オウンドメディアをゼロから立ち上げるには、コンテンツ設計、サイト構成、CMS選定、SEO・SNS連携まで、考慮すべき点が多くあります。ここではその基本ステップを整理してご紹介します。
必要なコンテンツ設計とサイト構成の考え方
まず重要なのは、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを設計することです。悩みや課題に寄り添う記事、サービス理解を促すコンテンツなど、ターゲットに合わせて用意します。
また、ユーザーが迷わず目的の情報にたどり着けるサイト構成も不可欠です。トップページから各カテゴリー、記事ページへの動線を意識し、回遊性の高い設計を行いましょう。
CMS選定とドメイン設計の基礎知識
オウンドメディアの運営にはCMS(コンテンツ管理システム)が必要です。代表的なものにWordPressがあり、初心者でも扱いやすく柔軟性が高い点が魅力です。
加えて、ドメイン設計も重要です。企業のコーポレートサイトと同一ドメインにするのか、別ドメインにするのかによって、SEOへの影響や管理方法が異なります。目的に応じた判断が必要となります。
SEOとSNS連携による集客導線づくり
せっかく作ったコンテンツも、見られなければ意味がありません。まずはSEO対策により検索流入を狙いましょう。キーワード選定や構造化、内部リンクの最適化が基本です。
さらにSNSとの連携によって、記事の拡散やコミュニティ形成も期待できます。検索とSNSの両軸からユーザーを導く導線設計が、成果につながります。
プロに任せる?オウンドメディア制作会社の選び方
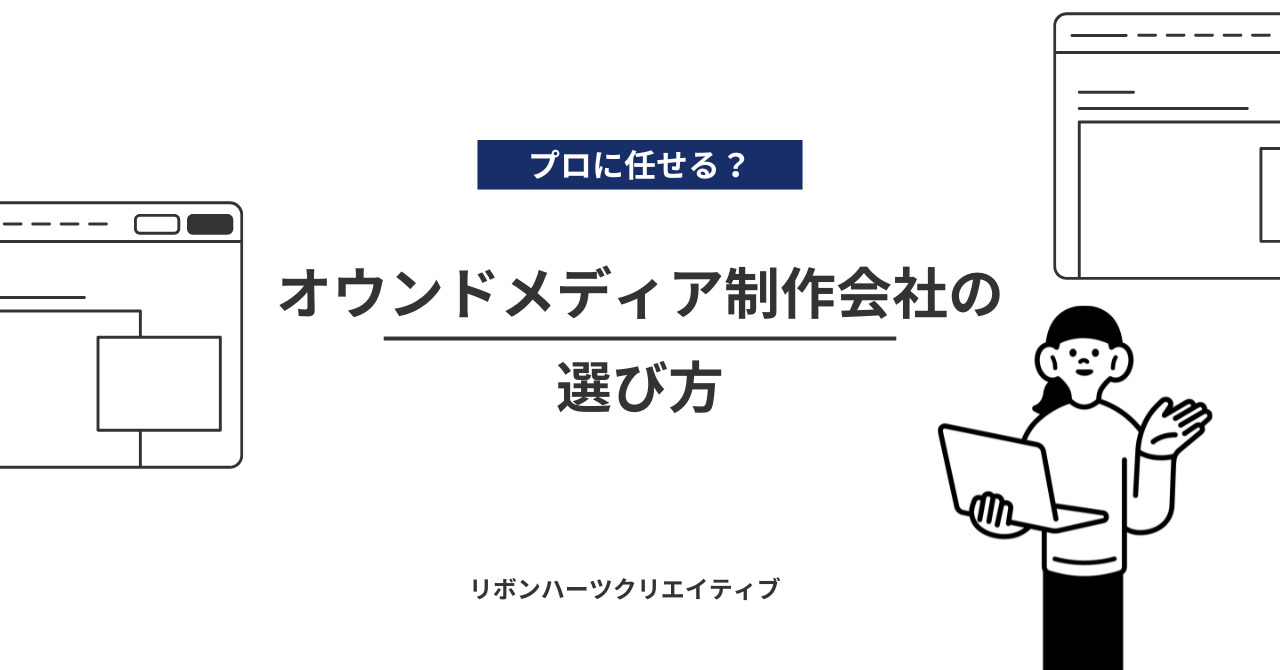
オウンドメディアの戦略や構築が明確になったら、いよいよ制作・運用フェーズに移ります。社内で完結できるのが理想ですが、リソースや専門性の問題から、制作会社に依頼する選択肢も現実的です。ここでは、外注すべきかどうかの判断軸と、依頼時のポイントを解説します。
内製と外注、どちらが向いているのか?
オウンドメディアには、企画・執筆・デザイン・分析など多様な業務が伴います。社内に十分なスキルと人員があれば内製も可能ですが、専門性やリソースが不足する場合は外注が効果的です。特に立ち上げ段階では、戦略設計から運用支援まで一括して対応できる制作会社を活用することで、スムーズなスタートが期待できます。将来的には、外注と内製を段階的に併用しながら、社内にノウハウを蓄積していく方法も有効です。
オウンドメディア制作会社の見極めポイント
外注先を選ぶ際は、単に制作費や知名度で判断するのではなく、「何ができるか」「どこまで対応してくれるか」を確認することが重要です。
戦略設計から運用改善まで一気通貫で支援できる会社であれば、長期的な成果が期待できます。過去の実績や得意業界、コンテンツの質なども、見極めの材料になります。
依頼時に伝えるべき要件と注意点
外注を成功させるには、目的・ターゲット・コンテンツ方針などの「前提情報」を丁寧に伝えることが不可欠です。情報が不足していると、意図と異なる成果物ができるリスクがあります。
また、運用体制や更新頻度、レポーティング体制など、継続的な運用に関わる点もあらかじめ共有しましょう。曖昧なまま進めると、双方にとってストレスとなる可能性があります。
リボンハーツクリエイティブが制作するオウンドメディア
リボンハーツクリエイティブでは、株式会社ソルクシーズが運営するWEBマガジン『安否確認LABO シニアの暮らしと介護と見守り』の制作を担当。高齢者の暮らしや介護に関する情報を発信し、見守り支援システム「いまイルモ」への関心を高める企業ブランディングを支援しています。
まとめ:企業オウンドメディアの未来と持続可能な運用
オウンドメディアは、企業の価値や信頼を長期的に育てる「資産」としての役割を持ちます。広告に頼らずにユーザーと接点を持ち続けられる一方で、「作って終わり」ではなく、継続的な運用と改善が欠かせません。コンテンツの更新、SEO対応、ユーザー体験の向上などを通じて、効果を持続させる必要があります。また、社内外での運用体制や改善サイクルの整備も成功の鍵です。今後はAIや音声検索、動画など新たなメディアへの対応も求められるでしょう。オウンドメディアは、顧客や未来の仲間と信頼関係を築く重要なプラットフォームとして、企業の成長を支える存在になりつつあります。
ライタープロフィール

神澤 肇(カンザワ ハジメ)
リボンハーツクリエイティブ株式会社 代表取締役社長
創業40年以上の制作会社リボンハーツクリエイティブ(RHC)代表。
企業にコンテンツマーケティングを提供し始めて約15年。
数十社の大手企業オウンドメディアの企画・制作・運用を担当。
WEBを使用した企業ブランディングのプロフェッショナル。
映像業界出身で、WEB、紙媒体とクロスメディアでの施策を得意とする。
趣味はカメラとテニス、美術館巡り、JAZZ好き。